
歌川広重-名所江戸百景-13-春-下谷廣小路 解説
現在の住所:台東区上野3丁目 松坂屋
緯度経度 :緯度35.7102:経度139.7745
出版 :1856年9月 年齢:60歳
解説
<1> はじめに
「下谷廣小路」は、江戸の下町文化と交通の要衝を鮮やかに描き出した作品です。
にぎやかな町人文化が息づく場所であり、広重は往来する人々や町並みを通して江戸の活気を表現しました。
「廣小路」とは火除地(ひよけち)に由来する広場のことです。
江戸の町は度重なる大火に見舞われたため、火の延焼を防ぐ目的で広い道や空き地が設けられました。
その空間が人々の生活に取り込まれ、賑わいの中心となったのが「廣小路」です。
<2> 下谷広小路とは
下谷は現在の台東区上野から浅草にかけての地域です。
江戸時代、上野寛永寺の門前町として栄え、多くの町人や職人が暮らしました。
火除地として設けられた広小路は、江戸の交通や商業の要所に発展しました。
市場や芝居小屋、露店が立ち並び、江戸っ子たちの社交場となりました。
江戸の「山の手文化」が武家屋敷や大名庭園を基盤とするのに対し、下谷の広小路は町人文化の象徴です。
芝居や見世物小屋、屋台が集まり、庶民の娯楽を支えました。
<3> 絵の見どころ
広重は通りを行き交う人々を細やかに描写しています。
買い物客、芝居小屋に向かう群衆、商人の姿などが活気を伝えます。
広小路には仮設の芝居小屋や見世物小屋が多く並び、賑やかな看板や幟が描かれています。
当時の大衆文化の息吹を感じられる場面です。
道がまっすぐ伸び、両側に町屋が立ち並ぶ構図です。
火除地の広さを生かした空間が、江戸の都市計画と庶民生活の交錯を示しています。
人々が楽しげに行き交う姿は、ただの風景ではなく「庶民の日常」と「娯楽の場」が一体となった江戸の独特な魅力を映しています。
寛永寺に向かう広小路が主体です。
広小路の呉服屋松坂屋を大きく描いています。
名古屋に始まる呉服商伊藤屋が、1768年 に上野の松坂屋を買収して営業した呉服屋です。
店前に立つ屋根付きの看板には「呉服云々」と書かれています。
中央やや左の建物は髪結床です。
<4> 江戸庶民にとっての広小路
広小路は芝居小屋や寄席、見世物小屋の立ち並ぶ娯楽の拠点です。
猿回しや講談、浄瑠璃といった庶民文化がここから発信されました。
通りには屋台や露店が並び、団子や寿司、駄菓子などを楽しめました。
江戸の「食べ歩き文化」は、広小路のような場所から育まれました。
下谷広小路は上野と浅草の中間に位置し、多くの人や物が行き交う場でもありました。
旅人や商人にとっても立ち寄りやすい便利な場所でした。
<5> 現代の下谷広小路を歩く
現在の台東区上野や御徒町一帯に「広小路」の地名が残っており、当時の記憶を伝えています。
「上野広小路駅」という駅名にもその歴史が反映されています。
現代の上野・御徒町は百貨店や飲食店が並び、江戸の時代から続く「商業と娯楽の街」としての役割を維持しています。
上野恩賜公園や不忍池、浅草へのアクセスの良さも相まって、広重が描いたような「人の集まるにぎやかな場所」としての性格は今も健在です。
<6>観光ガイド
①上野広小路駅周辺散策
現代の繁華街を歩きながら、江戸のにぎわいを想像できます。
②御徒町の商店街
江戸時代の職人町の伝統を引き継ぐ買い物の場です。
➂上野恩賜公園
広小路からすぐ、寛永寺や博物館、美術館が点在する文化の場所です。
➃浅草への道
江戸時代同様、広小路を経由して浅草寺を訪れるルートは観光にも最適です。


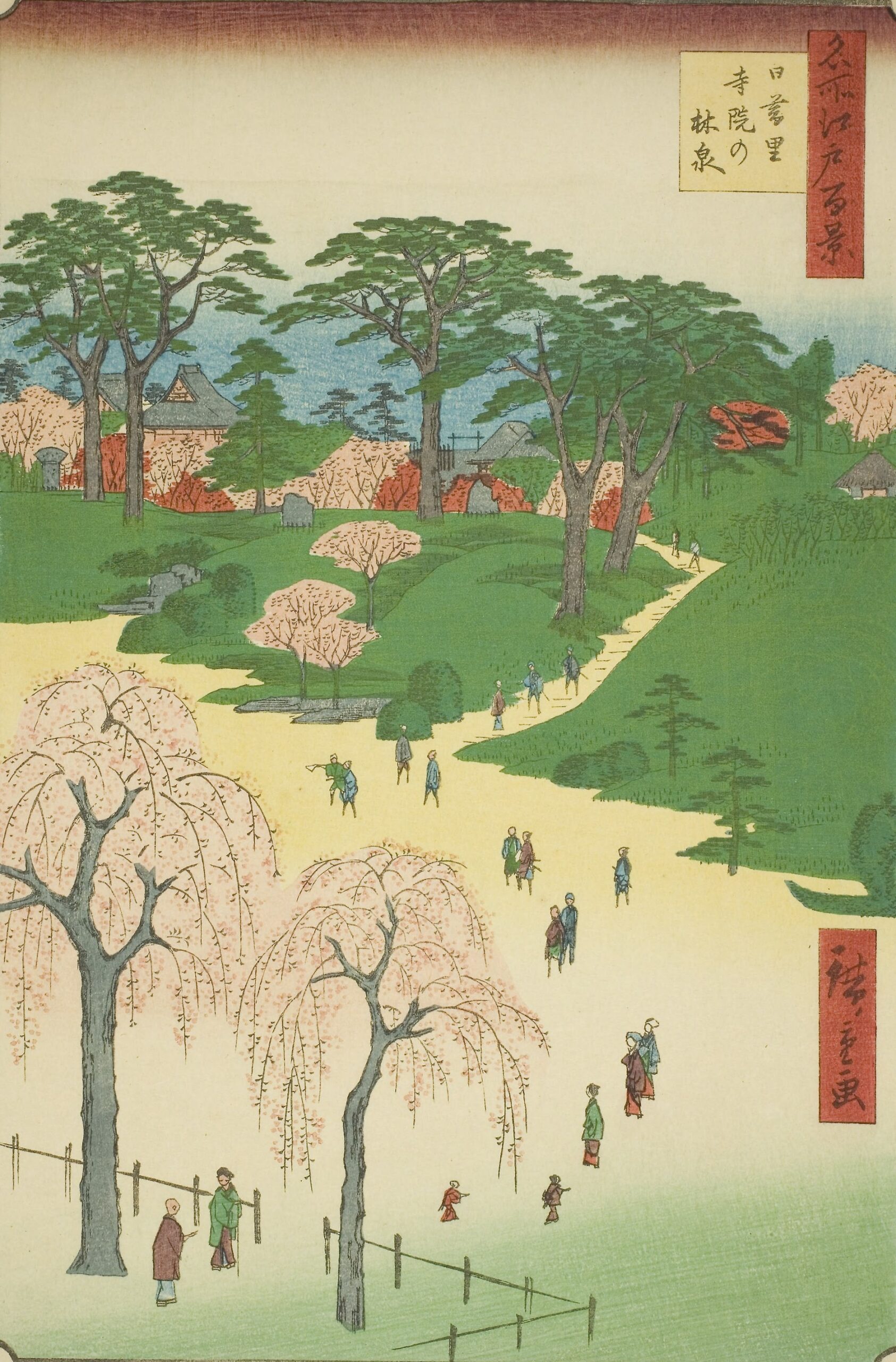
コメント