御油宿から吉田宿まで10.3km 北緯34度46分00秒 東経137度23分23秒
吉田宿は、東海道五十三次の江戸側から数えて34番目の宿場です。
601年の伝馬朱印状があり、東海道が設定された当初からの宿場でした。
江戸の日本橋より西方約287kmに位置します。
東の二川宿とは1里約6.1km、西の御油宿とは約10.5km離れております。
町並は23町約2.6kmの長さです。
吉田城城下町と湊町(吉田湊、船町)を合わせた宿場町でした。
表町12町と裏町12町の計24町で宿を構成されています。
本陣が2軒、脇本陣が1軒、旅籠は65軒でした。
戸数は約1,000軒です。
人口は5,000から7,000人です。
飯盛女が非常に多くいました。
本陣のあった札木町は吉田城大手門のそばにありました。
人馬継立の問屋場もあったため、中心として賑わいました。
現在の愛知県豊橋市中心部になります。
豊橋市は、三河地方における経済・交通の中心です。
市の人口は約37万人で愛知県内5番目の都市です。
中世から江戸時代まで市の中心部は吉田です。
吉田という地名は全国各地にあったため、三州吉田と呼ばれています。
吉田は豊川と朝倉川の合流地点であり、渥美郡、宝飯郡、八名郡の境目に当たります。
幕末の石高は7万石で、岡崎藩や西尾藩を上回って三河国内では最大でした。
①「保永堂版」
目の前は豊川です。
豊川にかかるのは豊川橋(吉田大橋)です。
この橋は長さ220メートルの大きな橋です。
右は吉田城の天守閣でsy。
城には升目状に足場が組まれています。
左官職人が壁の補修を行っています。
足場の上方には、鳶職人が遠くの景色を楽しんでいます。
②「行書版」
吉田大橋から今橋城(吉田城)を眺める構図です。
白帆の船が並び、豊川の水量の豊かさがわかります。
また、吉田橋の大きさが実感できます。
③「隷書版」
6月15日 天王祭りとあります。
祭りのにぎやかさが表現されています。
④「北斎版」
吉田大橋から遠くの山並みを眺めています。
ここでは、吉田城の方角が描かれていません。
⑤「旅画像」
本陣跡の石碑です。
東海道400年祭りイベントののぼりです。
⑥「スタンプ画像」
JRの駅イベントスタンプです。
保永堂版

行書版

隷書版

北斎版

旅画像


スタンプ画像



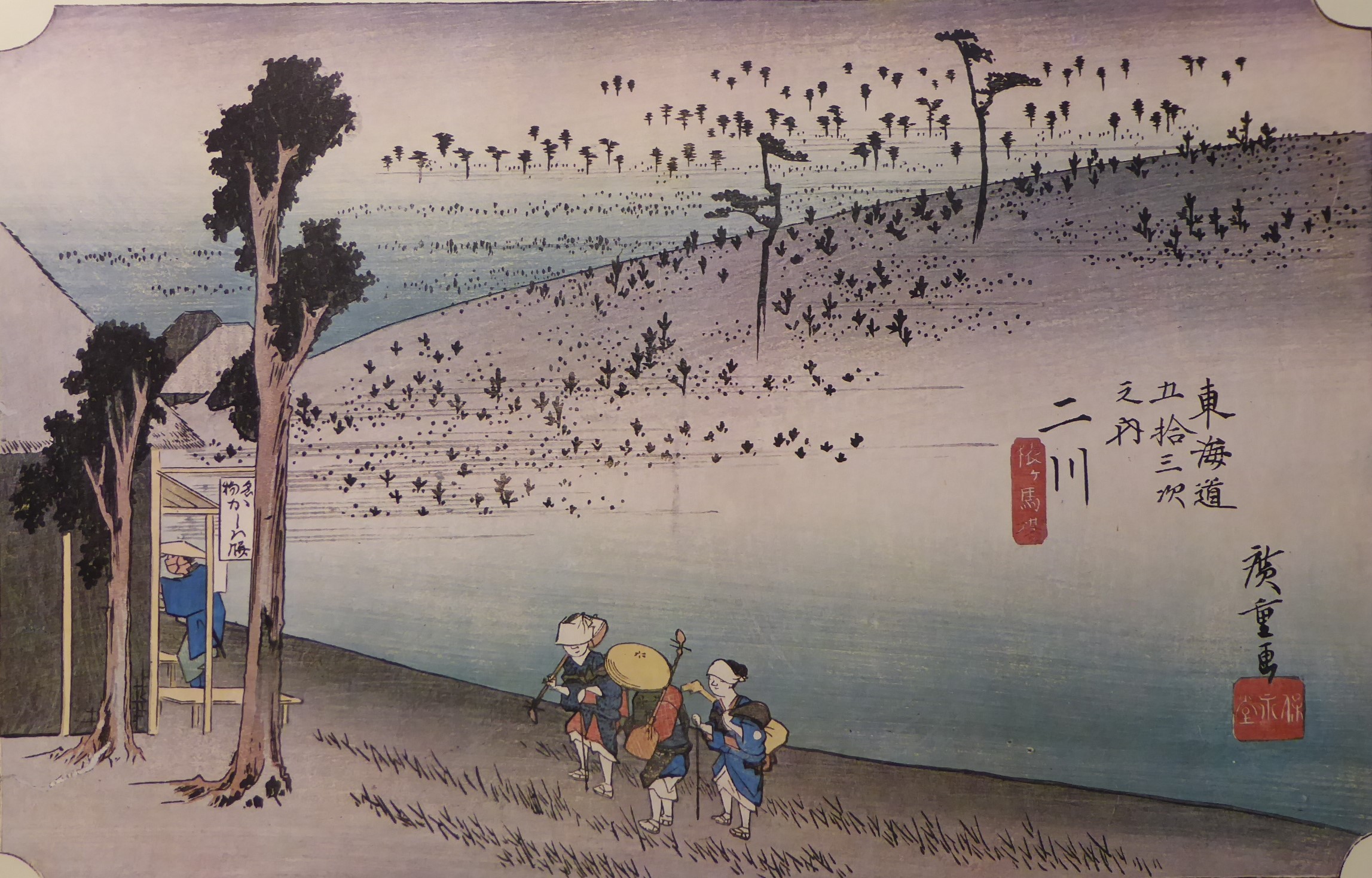
コメント